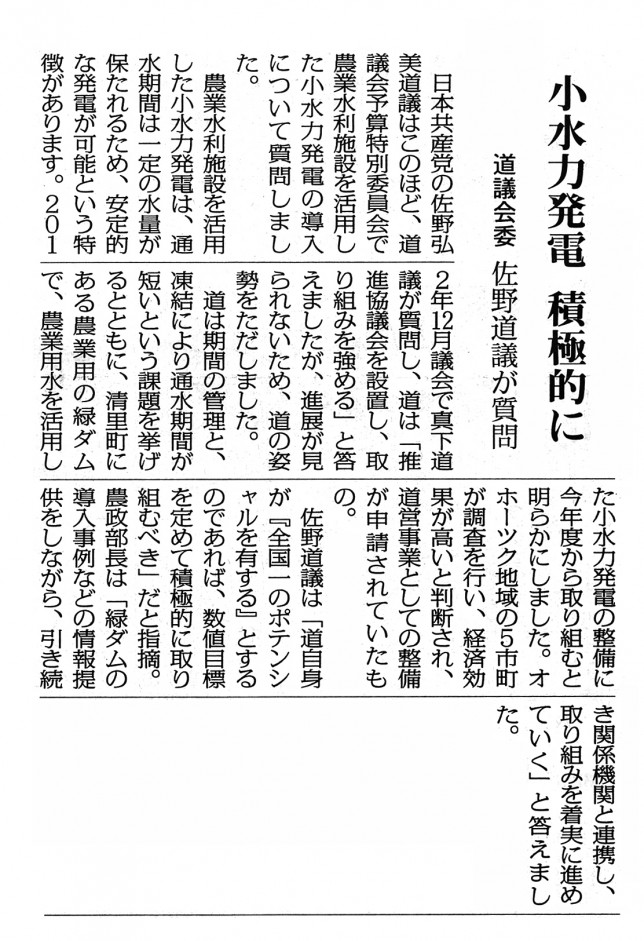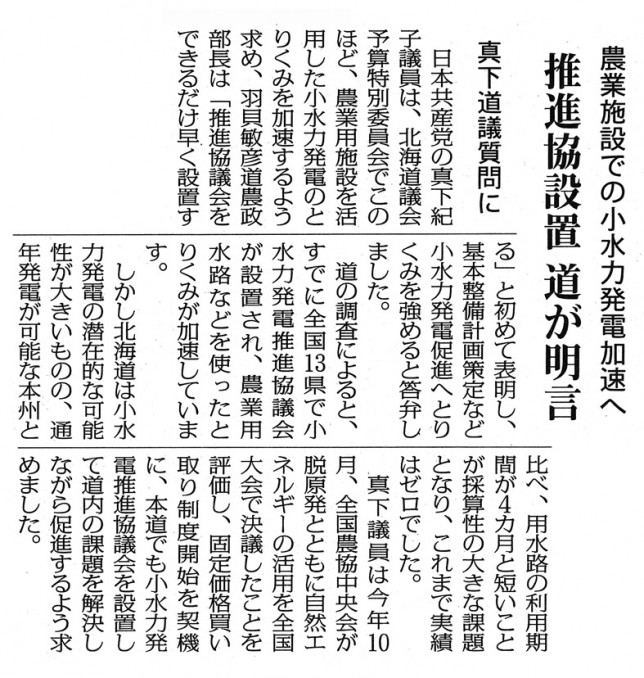真下道議が再生可能エネルギー 浜頓別町を視察
自然再生エネルギーを地域経済に生かそうと、福島第一原発事故前からとりくむ浜頓別町を訪ねました。
風力発電「はまかぜちゃん」(出力990㌔㍗)は、2001年にNPO法人北海道グリーンファンドの会員の電気料金の一部と、賛同する個人団体の出資で建設されました。また廃校となった小学校のグランド跡地などの町有地を使い、太陽光発電施設を建設。今年2月から北電への売電を開始しています。
福島第一原発事故が起きる10年も前から「原発や化石燃料に頼らないまちづくり」をめざしてきました。南尚敏副町長は自然エネルギーの導入推進について「エネルギーの地産地消を地域経済に生かしたい」と抱負を話しました。
真下議員は「原発に投じる財源を道北の脆弱な送電網にまわすなど政策転換も求めたい」と述べました。
浜頓別町の魅力にひかれて移住しその後、町議会議員となった宮崎美智子浜頓別町議が同行しました。
自然再生エネルギーを地域経済に生かそう
風力発電施設「はまかぜちゃん」 しんぶん赤旗記事2016.4.29
4月27日、28日は日本共産党道議団の視察で宗谷地方の枝幸町と浜頓別町に伺っています。その後、帰旭し、中心街で戦争法施行に抗議するスタンディングが行われている会場へ。日本共産党道議団の3人と旭川市日本共産党市議1人の4人が力強く声をあげました。
道議会予算特別委員会
農業用水利施設活用で安定的な発電可能
佐野道議が質問 しんぶん赤旗記事2016.4.26
2012年12月に真下道議が小水力発電の推進を求め質問し、道が取り組みを強めると回答していましたが、進展が見られないため、佐野道議が道の姿勢をただしました。
2012年12月 真下道議が小水力発電の推進を求め質問した内容
真下道議 議会質問 農業施設で小水力発電
2012年(平成24年)12月19日第4定例道議会 予算特別委員会第2分科会
北海道議会予算特別委員会でこのほど、農業用施設を活用した小水力発電のとりくみを加速するよう求め、羽貝敏彦道農政部長は「推進協議会をできるだけ早く設置する」と初めて表明し、基本整備計画策定など小水力発電促進へとりくみを強めると答弁しました。
道の調査によると、すでに全国13県で小水力発電推進協議会が設置され、農業用水路などを使ったとりくみが加速しています。
しかし北海道は小水力発電の潜在的な可能性が大きいものの、通年発電が可能な本州と比べ、用水路の利用期間が4カ月と短いことが採算性の大きな課題となり、これまで実績はゼロでした。
真下議員は今年10月、全国農協中央会が脱原発とともに自然エネルギーの活用を全国大会で決議したことを評価し、固定価格買い取り制度開始を契機に、本道でも小水力発電推進協議会を設置して道内の課題を解決しながら促進するよう求めました。
しんぶん赤旗記事2012.12.28