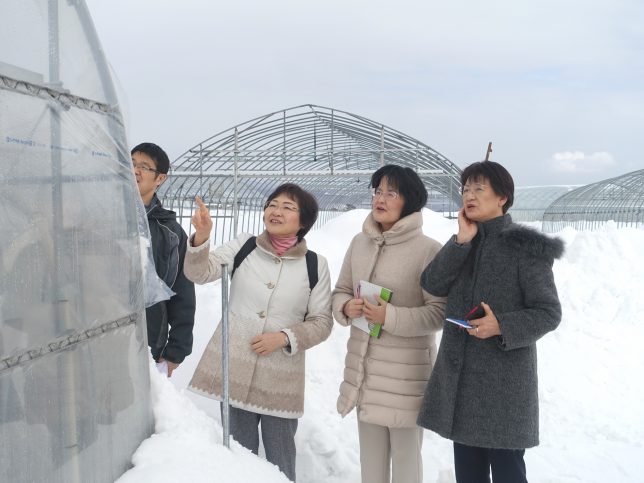食と観光対策特別委員会 バリアフリー観光 調査・意見聴取へ 2017年8月2日(水)
日本共産党道議団は7月に 南西沖地震から24年を経る奥尻町を訪問し、 バリアフリー観光の取組を調査しました。
しんぶん赤旗記事2017. 8. 29
現地での要望も踏まえ、8月2日(水)食と観光対策特別委員会で真下紀子議員がバリアフリー観光の推進 について質問しました。道観光局の木本晃観光振興監は観光の関係団体などで構成する「 バリアフリー観光推進検討委員会」で検討・調査し、バリアフリー観光を本格的に推進すると表明しました。

奥尻町では、2年間にわたって檜山振興局と管内の7町が共同し、 国のバリアフリーレジャー推進事業を実施してきました。 店舗や宿泊施設では、手すりやスロープを設置、 和室にベッドを置くなどして、 それをホームページや宿泊の予約サイトで案内をしてきました。 また、完備できないハード面をカバーするため、 観光協会が中心となり観光介助士という資格を取得して、 バリアフリー観光の振興にとりくんでいます。その一方で、 離島では、資格取得の研修に交通費負担が少なくなく、 バリアフリー車両の移送費が嵩むなど、 普及にあたっての課題があります。真下議員は、 人材育成やバリアフリー車両の確保など、具体的な課題を示し、 バリアフリー観光の推進に向けて検討を求めました。

道観光局は、バリアフリー観光の定着・拡大をはかるため、 観光関連施設や移動手段などのバリアフリー対応の促進や介助する 人材の育成のほか、 情報案内機能の充実や受入側のホスピタリティの向上などの課題が あると認識を示しました。そのうえで、 一般社団法人日本UD観光協会が認定した「観光介助士」 97名が、 道内で旅行会社の添乗員やバリアフリー対応の宿泊施設のスタッフ などとして活動しているとのべ、研修会などを通じて「 観光介助士」の活動状況や役割を紹介するとともに、 観光振興機構と連携して人材育成などの地域の主体的な取組を支援 していくと答弁しました。また、 バリアフリー車両の確保など広く地域の実情や課題の把握に努め、 国への要望を含め、対応を検討すると答えました。
真下議員は9月に開催されるきょうされん全国大会ではバリアフリ ーの宿泊施設の確保が困難だったことも紹介し、 当事者の声も聴くなど、課題解決に向けたとりくみを求めました。 木本観光振興監は、「福祉や観光の関係団体などで構成する『 バリアフリー観光推進検討委員会』 でバリアフリー観光の推進方策を検討し、 観光関連施設等のバリアフリー対応の状況について調査を実施する とともに、市町村や関係団体、 ハンディキャップのある方々から意見を聞いて、 誰もが利用しやすい観光地づくりの取組に活かす」と答えました。
しんぶん赤旗記事2017. 8. 29